老後設計のキーワードは、夫婦で“もしも”のシミュレーションです ~夫婦のiDeCo・NISAは「合わせ技」で活用を~
こんにちは、田中です。
年金制度は、原則「1人1種類」になります。これは、一人ひとりの最低限の生活保障を目的としていて、重複してもらうことを抑える設計になっているためです。
公的年金制度には大きく分けて3つの年金:
- 年金の種類:【1階部分】基礎年金 ⇒ 【2階部分】厚生年金(報酬比例)
- 老齢年金 : 老齢基礎年金 ⇒ 老齢厚生年金
- 障害年金: 障害基礎年金 ⇒ 障害厚生年金
- 遺族年金: 遺族基礎年金 ⇒ 遺族厚生年金
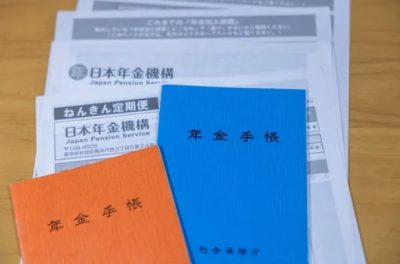
原則:同じ種類の年金は1つだけ選択(併給不可)
- 例えば、「老齢年金」と「障害年金」の両方に該当する人は、65歳前にはどちらか一方を選択する必要があります。
例外:種類が異なる年金は併給できる
- 65歳以降になると、「老齢年金」と「遺族年金」など、種類の違う年金を併給できるケースがあります。
老後設計が狂う!?配偶者が亡くなった後の生活変化の現実
夫婦で年金をベースに老後の生活設計をしていた場合、配偶者が亡くなると収入が大きく減少する可能性があります。
例えば:
- Aさん:老齢基礎年金+老齢厚生年金(年間180万円)
- 配偶者Bさん:老齢基礎年金(年間80万円)
合計:260万円 → 配偶者Bさん死亡後、Aさんの年金のみ(180万円) 収入が30%以上ダウンの可能性あり!?
こうならないための老後設計とは!?
① 私的年金の準備で備えることを検討しよう
公的年金は、最低限の生活保障が目的です。夫婦2人分で設計していた生活費が、配偶者が亡くなることによって一気に減収となり、生活が立ちゆかなくなってしまうことも!?
- 個人年金保険 ・・・民間の保険会社が提供する自分年金。年金を補完する役割として使える。死亡時に配偶者が受け取れるタイプもあり。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)・・・掛金が全額所得控除となる節税効果の高い自助年金制度。60歳以降に年金または一時金で受け取れる。配偶者の備えにも吉。
- NISA・・・長期・分散・積立投資に適した制度。老後資金形成の柱として吉。死亡時には投資分が遺産として配偶者に残る可能性あり。
- 終身保険・・・死亡保障がある保険。現金化も可能で、相続対策や葬儀費用としても使える。
②生活防衛資金の確保をしよう
配偶者が亡くなると、年金の切り替え・減額などの一時的な収入減少に対応できる現金が必要です。目安として生活費2年分の現金や低リスク資産を確保しましょう。
- 生活費2〜3年分の現金確保・・・突発的な出費や遺族年金支給までのタイムラグに備える。生活費が月20万円なら、少なくとも480〜720万円を目安に。
- すぐに使える形で保有・・・普通預金・定期預金など、すぐに引き出せる流動性の高い形で保有しておく。
- 貯めるタイミング・・・退職金や賞与を活用して、退職前から計画的に準備すると吉。
③長寿リスクへの備えをしよう
人は、収入(入ってくるお金)が無くなると、たとえ蓄えがあったとしても不安に思いがちです。特に女性は、配偶者が亡くなり一人になった場合、長生きリスクが高いと言われます。
- 長寿年金(民間)・・・一定年齢(例:85歳)から亡くなるまで年金がもらえる保険。長生きするほど得になることも。
- リバースモーゲージ・・・自宅を担保にお金を借りる制度。住み続けながら老後資金を確保できる。ただしリスクもあるため検討要。
- 繰下げ受給・・・公的年金の受給開始を最大75歳まで遅らせると、年金額が最大84%増に。ある程度貯えがあるようであれば、年金受給開始を遅らせることを検討してみては。
④住宅ローンの完済・住居コストの削減を検討しよう
- 定年までに住宅ローン完済・・・退職前に完済する計画を立て、年金生活にローンを持ち越さないプランをたてる。
- 持ち家 vs 賃貸の検討・・・賃貸の場合、更新料・家賃上昇リスクもある。高齢者の賃貸入居拒否される可能性もあり。
- リフォーム vs 住み替え・・・高齢期を見据え、段差のない住まい・病院の近くなどに住み替える選択肢も考えてみては。
⑤夫婦での年金戦略を可視化しておく
配偶者が厚生年金加入中に死亡した場合、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。ただし、自身の老齢年金(特に厚生年金)との併給調整があるため、受給額は全額ではない場合も。どちらかが亡くなったときに残る年金がいくらかを事前に知っておくと安心感が違います。
- ねんきん定期便・ねんきんネットの活用・・・自分・配偶者の将来の年金見込額を確認する。
- 夫婦の年金一覧を作成・・・老齢年金、遺族年金、障害年金の該当有無と見込額を整理。
- 年金併給パターンの確認・・・老齢厚生年金+遺族厚生年金など、併給可能なケースを調べる。
知っておくと安心なポイント
- 遺族厚生年金の計算対象は、「報酬比例部分」のみ(定額部分や加給年金は含まれない)
- 遺族厚生年金は、一定の子がいない場合、40歳未満の妻は5年間の時限支給
- 遺族厚生年金は、妻が40歳以上65歳未満であれば「中高齢寡婦加算」がプラス(一定条件あり)
- 遺族厚生年金は、自動的には支給されないので、必ず手続きが必要
- 自分の老齢厚生年金と重複する場合は一部カット(併給調整)されることもあり
- 遺族基礎年金は、一定の子どもがいる遺族が対象
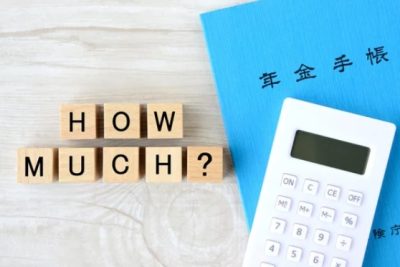
夫が先に亡くなると、妻の生活資金が急減!?
遺族厚生年金の額は、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3(=75%)が支給される、というのが原則です。この「報酬比例部分」というのは、夫の現役時代の給料やボーナスに応じて決まる年金部分です。
①遺族厚生年金の金額の基本的な仕組み
- 夫が厚生年金に加入していた場合、亡くなると「遺族厚生年金」が、妻や子に支給されることがあります。
②遺族厚生年金の金額はどう決まるのか?
- 原則:遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3(=75%)
- 例外:受給者(多くは妻)が65歳以上の場合、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の「調整(併給調整)」が入ります。
- このとき、以下の2つの金額を比較して、高い方が実際に支給される額になります。(65歳以上で、自分の老齢厚生年金がある場合)
③比較する2つの額
パターン1:亡くなった夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の 3/4
パターン2:亡くなった夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の 1/2 + 自分(妻)の老齢厚生年金(報酬比例部分)の 1/2
具体例で理解しましょう:
- 項目 金額
- 夫の老齢厚生年金(報酬比例) 年間120万円
- 妻の老齢厚生年金(報酬比例) 年間60万円
- ① 夫の年金の 3/4 → 120万円 × 3/4 = 90万円
- ② 夫の1/2 + 妻の1/2 → (120万円 × 1/2) + (60万円 × 1/2) = 60万円 + 30万円 = 90万円 → この場合、①と②が同額 → どちらでもOK(90万円支給)
- もし、妻の年金が多かったら? 妻の年金 : 年間100万円だった場合
- ②の合計 (120万×1/2)+(100万×1/2)=60+50=110万円 → ②の方が多い → 110万円が支給額になる
④結論:「3/4」だけじゃない!比較で高い方が支給されることも
65歳以上になると、「3/4」ルールだけで計算されるわけではなく、自分の年金が多い人は「1/2+1/2」の方が適用される方も。この比較は自動的に年金機構で行われますが、自分でも知っておくと安心ですし、将来の生活設計に役立ちます。

iDeCo・NISA活用は、夫婦の「合わせ技」が吉!?
iDeCoやNISAは、自分の名義・資金でしか運用できない完全な個人制度です。所得税や社会保険料とは異なり、税制優遇のある投資制度なので名義・口座の管理が厳格です。
夫が自分の名義で資産形成しておき、将来、妻の生活資金として活用することは可能です。
例えば:夫に収入があり、妻は専業主婦 の場合、
- 夫名義のNISAやiDeCo口座で積み立て → 将来引き出して妻に渡す
- 夫が亡くなった後、その資産を相続財産として残す
- 妻が高齢になってからの医療・介護・生活資金に充てる
NISAやiDeCoの「死亡時」の取り扱い・税務上の扱い・贈与や相続の関係
NISAやiDeCoは、死亡の時点で制度の非課税メリットは消滅し、相続財産としてカウントされます。
そのため、思っていたよりも相続税の対象額が増えてしまうケースもあります。
NISA口座で保有する株式や投資信託は、相続財産になります。ただし、そのままでは株式や投信を売却したり、配当金・分配金を受け取ったりはできないため、相続人は故人のNISA口座のある金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出し、財産を引き継ぐ手続きをする必要があります。
① 夫名義のNISAの死亡時の取り扱い
- 夫が亡くなった時点で、NISA口座の非課税枠は終了
- 口座内の資産(投資信託など)は、相続人の課税口座に払い出されるか、相続人が売却して現金化
- 相続財産として時価で評価され、相続税の対象になる
- 相続税評価は、元本でも売却益でもなく、死亡時の評価額になる
株式や投資信託は、その時点での含み益が非課税となり、その日の終値が相続人の取得価格になります。 注意したいのは、相続人がNISA口座を持っていてもそこには移すことはできず、同じ金融機関に設けた相続人の課税口座に移ります。
② 夫名義のiDeCoの死亡時の取り扱い
- iDeCoは、夫の死亡で契約終了
- 残された積立資産は「死亡一時金」として、指定の相続人(通常は妻)に支払われる
- 全額相続財産としてカウントされます
- 相続税評価は、原則、死亡時点の残高評価額
③ 生前に夫が引き出して妻に渡す場合 →「贈与」扱い
- 夫が自分のNISAやiDeCoから資産を取り崩し、妻に現金で渡したら「贈与」扱い
- 年間110万円までは贈与税非課税(基礎控除)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は「年金目的の制度」なので、通常は60歳以降に本人が年金として受け取る前提で設計されていますが、本人が亡くなった場合(特に60歳未満)には、以下のように取り扱われます。

【iDeCo】夫が60歳未満で死亡した場合の取扱い
夫が60歳未満で死亡(iDeCo受給開始前)
- iDeCoの受給資格年齢(60歳)に達していないため、「老齢給付金」としての支給はされない
- iDeCoはこの時点で**「死亡一時金(死亡給付金)」**に変わる
死亡一時金の受取人は?
- 原則:加入者が生前に指定した「死亡一時金の受取人」が優先
※iDeCoの運営管理機関や国民年金基金連合会に届け出ていた人 - 指定がない場合は、**民法上の法定相続人(例:妻や子)**が受け取ることになります
税金はどうなる?
- 相続税課税される(原則)
- 死亡時点のiDeCo残高(時価評価額)が相続財産に加算される
- 所得税・住民税非課税(死亡一時金は「遺産」なので、所得税はかからない)
- 相続税の対象であっても、以下の相続税の非課税枠が使えます:
- 配偶者:1億6,000万円 or 法定相続分のいずれか大きい方まで非課税
- その他の相続人も、「基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」あり
まとめ
- iDeCoは「死亡一時金受取人の指定」が可能 → iDeCoの死亡一時金の受取人は、明確に妻にしておくこと
- iDeCoは、夫が生前に引きだすとき、一括受取:退職所得(控除あり)or 年金受取:雑所得(公的年金控除あり)の選択制
- iDeCoの資産は、相続税以外に所得税や住民税はかからない(ただし受取後の運用には注意)
- 相続時、NISAの非課税メリットは消滅する
- 生前にある程度、NISAから現金化しておいて妻に分割贈与しておくのも一案
- 多額を一括で渡すと「贈与税」や「相続税の加算対象」になる可能性あり
- iDeCoは「死亡保険金」ではないので、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)は使えない
- ただし、相続税を払った場合は、運用益を売却した際に取得費加算の特例が使える可能性あり(要件あり)
こうした制度の違いや税制の知識を持っておくことで、大切な家族のために、より有利な老後設計・資産移転が可能になります。


















